「実運送体制管理簿」義務化はザル法?
真因は有識者会議か、それとも国交省の怠慢か
抜け道だらけの政策
実運送体制管理簿の作成義務は、今春施行された貨物自動車
運送事業法で定められている。この政策は、特に中小運送事業者が
悩んできた多重下請構造の是正を目的としている。
具体的には、下請事業者を利用する元請事業者に対し、運送案件ごとに
下請事業者の社名などを記載した実運送体制管理簿の作成を
義務化するというものだ。
【画像】「マジかぁぁぁぁ!」 これが自衛官の「年収」です!
グラフで見る(計7枚)
しかし、この政策には多くのケースで作成義務を回避できる
“抜け道”があった。
詳細については、筆者(坂田良平、物流ジャーナリスト)が
以前書いた記事「“抜け道”発覚で「物流改革」破綻!?
ネットで広まる「実運送体制管理簿」回避術! 国交省の
お粗末設計、多重下請構造の闇ふたたび?」
(2025年3月31日配信)をご覧いただきたい。
簡単にいうと、下請取引に参加する運送事業者同士が利用運送契約を
結べば、実運送体制管理簿の作成義務を免れるというものだ。
さらに、記事では実運送体制管理簿を作成しなかった場合の罰則が
ないことも指摘した。このことから、政府が本気で多重下請構造の
改革や物流革新を実現しようとしているのか疑問を呈している。
記事に寄せられた反響
先の記事について、筆者には多くの意見や反響が寄せられた。
最も多かったのは、「実運送体制管理簿の作成義務が周知
されていない」という声だった。
・A:荷主や元請事業者が、今春から実運送体制管理簿の作成が
義務化されたことを知らない
・B:(中堅元請事業者の営業所長からの声)
社内の他営業所の所長でも、実運送体制管理簿作成義務を
知らない人がほとんどである
Bに似たケースでは、トラック協会が主催する研修会が5月以降に
開催予定で、急いで準備や勉強をする必要はないと考えている人が多く、
法令遵守意識が欠けているという声もあった。次に、こんな声もあった。
・C:自社よりも多重下請構造の上位にいる運送事業者、
元請事業者、荷主が、どのような契約を結んでいるのか
(利用運送契約なのか)がわからないため、自社に実運送体制管理簿の
作成義務があるのかどうかが不明
・D:そもそも元請事業者がわからない。
自社が何次請けに該当するのかも不明であり、したがって
当然実運送体制管理簿の作成義務が課されるのかどうかも不明
CとDのケースでは、自社の立ち位置が不明なため、
法令遵守意識はあっても、どのように行動すべきかが
わからないという状況だ。さらに、利用運送事業者からは
以下のような声もあった。
・E:利用運送事業者にとって、協力会社(≒下請事業者)の
リストは営業資産でありノウハウなので、元請事業者には
「当社が実際に運送を行っています」と嘘をついて報告している
また、実運送体制管理簿作成の義務化が新たな下請けイジメを
生んでいるとの指摘もあった。
・F:本来は元請事業者が実運送体制管理簿を作成しなければ
ならないはずなのだが、1次下請である当社に作成を丸投げしてくる
・G:(実運送を担う運送事業者から)元請事業者から毎日、
「運行車両のリストを提出しろ」といわれ、
実運送体制管理簿作成には関係のないはずの車両番号や
ドライバー名まで求められ、業務負担が増えた
最後に、実運送体制管理簿作成に真剣に取り組もうとする
事業者からは、次のような声も寄せられた。
・H:運輸支局に実運送体制管理簿作成について質問を
行ったところ、「下請事業者との契約を利用運送契約で
再締結すれば、管理簿作成は必要ありませんよ」と、
抜け道を指南された
抜け道放置、政策の信頼失墜」
反響のなかには、法令遵守や物流革新政策の実行について
疑問が生じる内容もあった。一方で、C、D、Hのように
真面目に法令遵守をしようとする運送事業者が独り相撲を取らされ、
「正直者が馬鹿を見る」
状況に追い込まれるケースがあるのは、とても悲しい。
実運送体制管理簿の作成義務は、物流革新政策の始まりに過ぎない。
・大手荷主への物流改善義務化
・中長期的な計画の策定
・CLO(Chief Logistics Officer)の選任義務化
など、物流革新に向けた新しい取り組みが2026年春から施行される。
しかし、現時点で法律に抜け道が見つかり、政府の物流革新政策は
出だしでつまずいた。実際、冒頭に挙げた記事に対して
SNSでは、「政府は本気で物流革新を進めるつもりはなかった」
という主旨の投稿も見られた。
筆者が関係者に取材した限りでは、「あえて抜け道を設けた」
という陰謀論は信ぴょう性が薄い。
「うっかり抜け道を見落としていた」
というのが真実のようだ。また、各地方の運輸支局が同じように
抜け道を案内していることから、国土交通省が今春の法施行前に
この抜け道を把握し、局内で共有していたことがわかる。
つまり、国土交通省は抜け道を知りながら法改正を行わず、
塞ぐことを怠ったということだ。もしこれが事実であれば
(おそらく間違いない)、実運送体制管理簿の抜け道は
「国土交通省の怠慢」
であり、実に嘆かわしい。
政府による事前発見の失敗
なぜ政府は、実運送体制管理簿作成の抜け道を法律施行前に
見抜けなかったのだろうか。筆者は、従来の有識者会議を基にした
政策立案の方法が、限界に達していると感じている。
誤解のないようにいっておくが、物流界の有識者は皆、深い知識を
持っている。筆者も何人かの人たちと面識があり、尊敬している。
しかし、その人選には偏りがあり、アカデミックな方向に偏ったり、
大手事業者ばかりから選ばれる傾向がある。
どの有識者会議を見ても、同じ顔ぶれが並んでいる。
厳しくいえば、これらの人たちは
「実運送体制管理簿の抜け道を見つけられなかった人」
たちだ。こうした人選では、今後の物流革新政策でも同じような
失敗が繰り返される可能性がある。
そのため、以下のような新たな取り組みが求められるのではないか。
・国内運送事業者、倉庫事業者、物流システム会社、
マテハン会社などから、裁判の陪審制度のように、
有識者会議への参加者を無作為に選ぶ制度
・物流エコシステムに属する事業者から広く意見を募る仕組み
・SNSプラットフォームの協力を得て、投稿された意見を
集約し分析する手法の確立
特に物流従事者からは、政策に現場の声が反映されていないという
不満が多い。筆者は現場の声を偏重することにリスクがあると
考えている。現状維持のバイアスが強く、現場への過剰な利益誘導が
改善を妨げる可能性が高いためだ。
それでも、現場の声を含め、より広範で多くの意見を政策立案に
活用することは不可欠だと考えている。
物流革新政策の転機
生成AIの実用性は向上し、万件単位の意見を集め、その傾向を
分析するのも容易になった。この新技術を政策立案に
活かさない手はない。
初めに躓いた物流革新政策には、これ以上のミスは許されない。
2025年は中長期的な物流基本政策を取りまとめる物流大綱が
5年ぶりに刷新される。
政府には、よりよい未来のために、旧来のやり方に固執せず、
多様なアイデアを取り入れた優れた政策立案を期待したい。
【引用元:Merkmal】
https://carview.yahoo.co.jp/news/detail/4fb500aead7cb936f58233a9d3eec70e9229689b/
ずる賢い人は穴を見つけてそこをついてくる。
どのようなことをやっても一定の確率で
起こる事象かと思います。
一つずつ順に潰していくしかないでしょう。
初めから完璧な事をすることは困難ですので
ドンドン改善していけばよいと考えます。

福岡県【筑豊エリア】【北九州エリア】
飯塚市/田川市/嘉麻市/嘉穂郡/直方市/鞍手郡で
物流加工・発送代行・配送代行・商品保管(坪貸し)・賃貸倉庫・
物流倉庫アウトソーシング(委託)をお探しなら
株式会社TransportWunder(トランスポートヴンダー)へ
ご依頼ください。


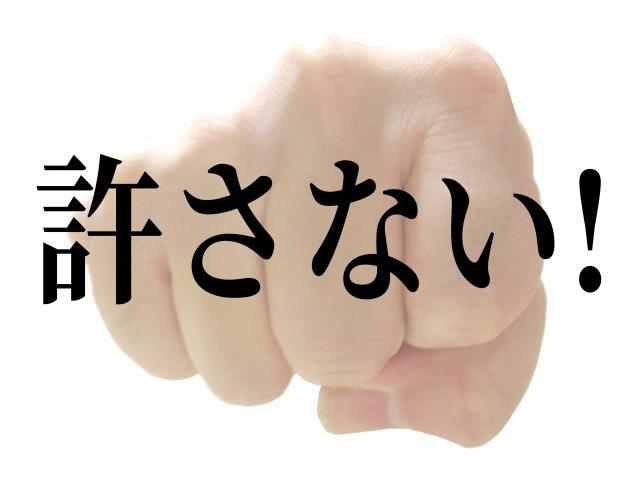

コメント